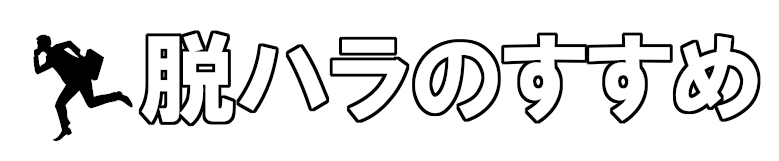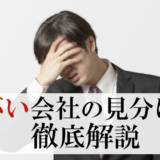あなたは以下のような働き方に悩んでいませんか?
- 上の意見が絶対
- 会議で発言しろ!と言われて発言すると怒られる
- 非効率が当たり前
日本人の働き方に対する考え方はムラ社会の色が強く、旧態依然としています。
まさに昭和な会社といった感じがします。
「働き方改革」という言葉だけが独り歩きをして、実際のところ、何も変わっていない職場が多い印象です。
そんな働き方に疑問を抱いていませんか?
私は過去に、職場いじめを黙認する会社と衝突した結果、何も変わらなかった挙句私は鬱病に。
その経験から学んだことは、時代遅れな働き方をする環境から抜け出すこと。
どんな方法で抜け出したのかを、具体的に解説していますので、最後までお読みください。
仕事観がおかしい!と感じる日本企業での働き方に見切りをつけた④つの理由

私は職場でパワハラや不当な退職勧奨など、理不尽ないじめを受けてきました。
その結果、心が疲れて鬱病に。
今振り返ってみると、時代遅れな働き方は非効率でストレスの度合いも大きかったなと。
私が転職を考えるきっかけにもなった④つの事例を挙げていきます。
➀年功序列が根深い
日本でも今どきは、成果主義の導入が進んでいると言われています。
しかし、実態は年功序列というケースも珍しくありません。
古いやり方にこだわった社歴の長い人が会社を牛耳っていて、意見を言おうものなら潰しにかかってくる。
全ての会社に当てはまるわけじゃないと思いますが、これが現実かなと感じます・・・
②上司が絶対の雰囲気
例えば、
- 有休が取得しづらい
- 上司より早く帰宅できない
- 何か意見したら干される
といったように、何をするにも自由がなく、上司の顔色を伺いながら仕事を進めていくという空気感に歯がゆさを感じたものです。
特に、会議のときに意見を求めてくる割には、意見をぶつけると圧力をかけてくるなど、理不尽な印象が拭えませんでした・・・
③効率よりも秩序を重視→無駄が多い
「今までこうやってきたから」と、まるでパワーワードのように用いられる効率を否定する言葉。
こちらが効率的なやり方を提案しても、受け入れる度量が会社になかったため悔しい思いを何度したことか!
新卒向けの求人ページには、「積極的に意見できる人材を求む」と書いてあったのに・・・
④いじめを見て見ぬふり
例えば
- 新規開拓の営業で上司に手柄を横取りされる
- 上司のミスを責任転嫁される
- 望まない仕事を押し付けられる
といったようなことがあっても、周囲は知らんぷり。
人事に相談しても「不満があるなら会社を辞めれば」という返答で、何も解決せずという状況。
何のためにこの会社に入社したのだろか?と自問自答する日々が続きました。
その結果、絶望から鬱になった事も。
仕事観がおかしい!と感じたらしなくて良い事

➀納得いかない事を受け入れる
- 「上司の意見だから」
- 「これまでやってきたから」
という理由だけで、自分の気持ちを飲み込むのは正直つらいですよね。
自分の意見や考えをしっかり伝え、ダメ元で職場の風土を少しずつでも変えるための行動、又は自らが環境を変えるアクションを起こしていきましょう!
②変わることを期待する
- 「いつかは変わるだろう」
- 「じきに良くなるはず」
と考えて待っているだけって、ちょっと考えもの。
実際のところ、動き出さない限り、何も変わらないもの。
変わりたいなら、自分からアクションを起こす必要性を感じます。
期待だけで時間を過ごすよりも、自分で変化を生み出すチャンスを探してみましょう。
時代遅れな日本企業の働き方が改善されない理由

➀同調圧力や他人軸が求められるため
日本の労働環境は、どうしてここまでおかしくなってしまったのでしょうか。
そこには、日本人特有の同調圧力や、他人軸に基づいた価値観が定着しているからです。
- 「自分は今日の仕事は片付いたが、他の人が働いているから帰りにくい」
- 「効率よく仕事を進めて早く帰りたいのに、周りの人にどう見られるか気になって、同じようにダラダラと仕事を進めてしまう」
これらの状況に思い当たる節はありませんか?
本来ならば、効率よく物事を進めて成果をあげることが仕事なのです。
それを実現して、誰かに迷惑がかかることはありません。
あなたが、しっかりと成果を上げて早く仕事を終えることが出来ているのなら、人の目を気にせず、堂々と帰っていいはずなのです。
②終身雇用時代の名残が根強いため
日本のおかしな労働環境をつくりあげた要因に、終身雇用の影響も無視できません。
年功序列の賃金制度のため、意欲や能力がなくても、長く居座った人が高い給料を得ることになります。
また、同じ会社にずっと居続ける前提にあるため、上司や同僚の顔色をうかがい、サービス残業や休日出勤を受け入れている習慣が出来てしまった、ともいえるでしょう。
時代遅れな会社に見切りをつけた私が取った行動

➀周りに流されないこと
おかしいと感じる労働環境から抜け出すには、人は人、自分は自分と考えることから始めてください。
会社の体質を変えるのは難しいので、まずは自分の働き方を変えていきましょう。
②異動願いを出すなどして配置転換を考える
部署によって、職場環境がずいぶんと変わる会社もあります。
今の会社が合わないと感じた場合には、退職をする前にまずは異動願いを出すなどして、配置転換を考えてみてもよいでしょう。
転職したのと同じくらい、働き方が変化する場合もあります。
会社を辞めずに済むので、収入が途切れないこともメリットです。
 たかのり
たかのり
私も転職を考える前にまず配置転換の打診をしています。
③転職をして働く環境を変える
社内に異動したい先がない場合や、異動願いが叶わなかった場合には、転職をして働く環境を変えるのもよいでしょう。
また、旧態依然とした労働環境に疑問を感じるなら、新興企業に目を向けてみるのもよいと思います。
私は、新興企業に転職したわけではありませんが、転職エージェントを活用したことで在職中の間に転職先を決める事ができました!
別の記事では、私の転職活動の実践記的な内容と、転職エージェントをおススメする理由について語っています。
併せてお読みください。
↓ ↓ ↓
 会社がつらい!辞めたいけど悔しい!転職という選択肢が正解だった話
会社がつらい!辞めたいけど悔しい!転職という選択肢が正解だった話
私も実際に活用した、おススメ転職エージェント③社

ここからは、私が実際に転職活動時に活用してみて、お勧めできそうな転職エージェント3社を解説していきます。
また、それぞれの会社に特徴があるので、まずは登録してみてあなたの求める条件に合うかどうかを確認するうえでも、3社ほど登録される事をおススメします。
また、登録自体は無料ですし、事前のweb登録は10分程でできます。加えて、コロナ禍を経てからは、リモート(事前確認は必要)でも登録もできるようになりました。
登録したからといって、必ずしも転職しなければいけないわけではありませんので、情報収集の一環としてお試し感覚で登録されてみてはいかがでしょうか?
※マイナビのプロモーションを含みます。
- 20代の転職に強い
- 2023年度オリコン顧客満足度総合1位
\ 20代の転職に強く、若手世代の満足度も高い /
- リクナビにはないサポートが受けられる
- 求人数が業界トップクラス
公開求人数:36万件以上(2023年3月30日時点)
- 転職支援実績No.1(2022年6月時点)
\ 転職支援実績と求人数は業界トップクラス /
- 業界最大級20万件以の豊富な求人数(2023年3月時点)
- 転職サイトとエージェントの2つの機能がある
- 20代から30代前半の若手登録者が7割
\ 若年層をターゲットにした求人が豊富 /
日本人の仕事観はおかしい! 私が時代遅れな働き方に見切りをつけた理由まとめ
この記事では、私がおかしいと感じた時代遅れな働き方に見切りをつけた理由とその後の行動についてお話してきました。
おさらいも兼ねてまとめていきます。
- 仕事観がおかしい!と感じる会社は旧態依然としていて何も変わらない
- 旧態依然とした会社に変化を期待するのは難しい
- 疑問を抱く日々が続くのであれば、社内の配置転換や転職などで環境を変える事も選択肢のひとつ
大切なのは、あなたがどうしたいのかです。
周りの意見に振り回されることのないよう、納得のいく働き方をしていきましょう!